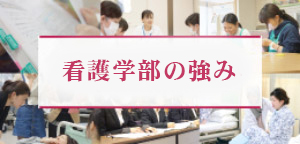本文
令和7年度 第1回ケア検討会
【テーマ】チームの見立てがすれ違うとき―共感と想像力から考える看護管理―
【日時】令和7年6月20日(金曜日)18時〜20時30分
【方法】ハイブリット(対面・オンライン会議)
【参加者】参加者22名:医療関係者12名、大学院生6名、教員4名
今回は、精神科病棟において多職種チームの見立てがすれ違う場面を取り上げ、共感と想像力を軸にした看護管理のあり方について検討を行いました。すれ違う具体的な事例としては、医師は「入院目的である生活リズム是正ができれば退院」とする一方、看護師は「退院後の支援も必要」と考え、チーム内での目標設定にズレに管理者としての葛藤が語られました。これまでは、職種ごとの視点の違いから見立てに差が出ることは少なかったのが、最近、職種ごとの信念や価値観の違いが顕在化し、意見が噛み合わない場面が表面化してきた現状や本来強みとなる他職種の多種多様な意見を「想像する力と共感性の促進」につなげたい思いが伝わってきた内容でした。
参加者からの意見では、職種の専門性や精神科特有の課題共有の難しさ(患者は自分の思いを言語化できず、家族の支援も乏しい)が共有され、相手の立場や価値観を一度受け止め、共感的に関わる姿勢の重要性や再入院率や患者満足度などのデータを用いて意見を論理的に伝える力も求められることが確認されました。
大学院生からは事例に沿って2本の論文の紹介があり、文献を用いて意見交換を行いました。組織論の考え方として「センスメイキング(意味づけの共有)」や「トランザクティブメモリー(役割理解と知識共有の仕組み)」が紹介され、顔の見える関係にとどまらず、役割と強みを活かす仕組みづくりの重要性が共有されました。
事例提供者は、本検討会を通じて様々な意見に触れ、自身の考えを言語化する中で、その難しさと重要性を実感したと振り返っていました。また、異なる立場の医師の背景や状況に思いを巡らせることで、多職種と関わる難しさと、相互理解の大切さを改めて認識し、こうした理解を一つずつ積み重ねていくことが、今後のチーム形成につながるという前向きな思いが述べられました。
【参加者のアンケート結果要約】
・多職種協働で情報共有しながら患者に向き合うことが当たり前と思っていたが、専門性高さやそれぞれが大事にしている事、目的のズレなどが生じることも容易に起こることがある。しかし、相手の特性を知ることで、上手に歩み寄ることができるかもしれないなど、人と人とのコミュニケーションの大切さや術も学んだ。
・精神科、児童という特殊性がありながらも、どの領域でも課題となっている多職種連携、他職種コンフリクト、明確な意思表明が出来ない患者の支援などが含まれており学びが深まった。
・精神科事例を通じ、患者様をとらえる視点、考え、思いを他職種と、共有することの難しさを知りました。 日々の自分達の看護や他職種の人の思い、関係性を見直す良い機会を頂いた。
・事例提供者にとって、事例状況と真剣に向き合うきっかけになり、その上で多くの視点から意見をいただくことでより深い気づきを得ることができる。また、参加者にとっても他施設の取り組みを知り、多職種連携について改めて考えるきっかけになるため、非常に有意義な時間であると感じた。
・多職種、年代、仕事に対する考えや意欲、私生活等様々な状況や考えスタッフに対して管理者 として自分がどうあるべきかということあらためて考えるきっかけとなった。